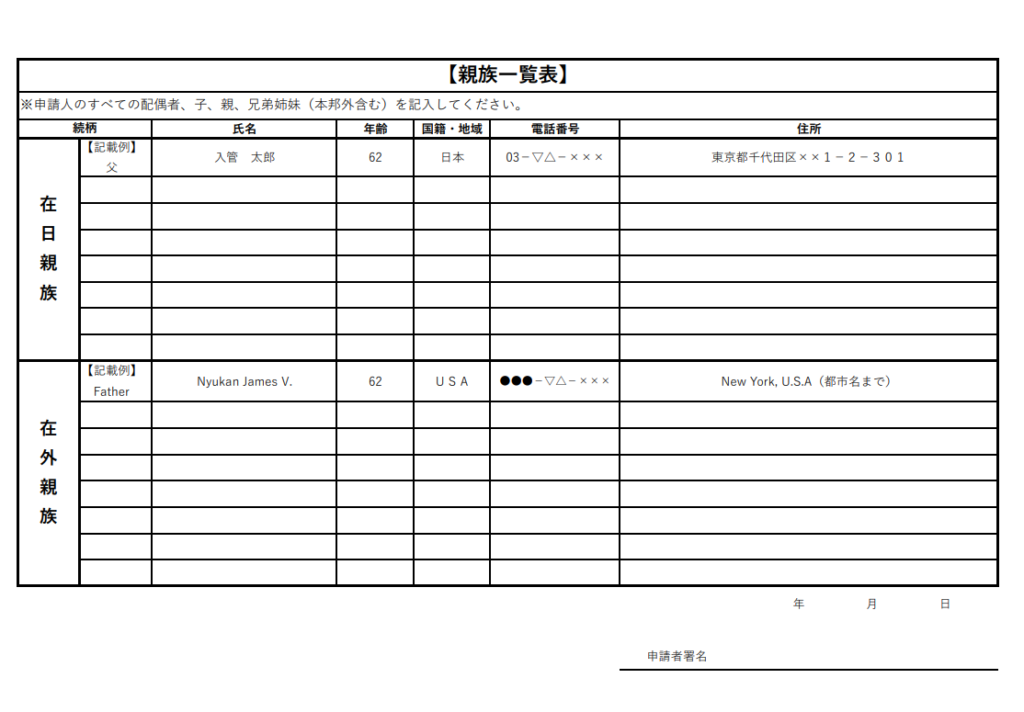在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請において、残念にも「不許可」となりうることもあります。資格変更の場合、在留期間が残っていれば、改めて再申請を行うか、更新の申請を行うことが可能です。しかし、更新申請の場合、審査で不許可となれば、必ず申請人ご本人が入管へ呼ばれ、不許可の理由説明とともに特定活動(出国準備)等への在留資格変更がなされます。(6,000円の申請手数料が必要です)
この際の特定活動(出国準備)は、出入国在留管理局が指定した日数だけ、日本から出国するにあたっての準備期間がもらえることになります。その期間は、一般的には30日又は31日となります。
ここで付与される在留期間が、30日か31日かで大きく変わってきます。すなわち、出国準備期間中に再申請ができるかどうかということです。結論から言えば、31日の場合は再申請が可能となります。入管の制度上、30日を超える在留資格の場合(31日)には、「特例期間」として在留期限から2ヶ月間、適法に日本に在留することが認められます。従って、再申請した後の2ヶ月以内に審査の結果を通知しなければなりません。
しかし、30日の場合は特例期間が認められません。再申請をしたとしても、特例期間がないため、出国準備のための在留期限が到来すると法律上不法残留(オーバーステイ)になってしまいます。審査期間が30日で終わるとは限りませんので、申請も受け付けてもらえないかもしれません。この場合は、必要な書類を揃えて各審査部門での事前確認を受けることです。ただ、申請が受け付けられるとしても、30日以内での結果判明は難しいと思います。
不許可となった際に、特定活動(出国準備)30日や短期滞在30日に変更された方は、この間に「在留資格認定証明書交付申請」の申請手続きを行い、いったん出国することをお勧めします。