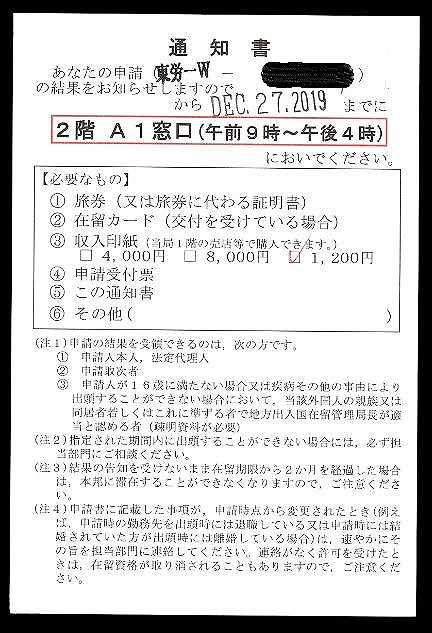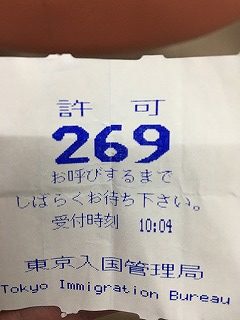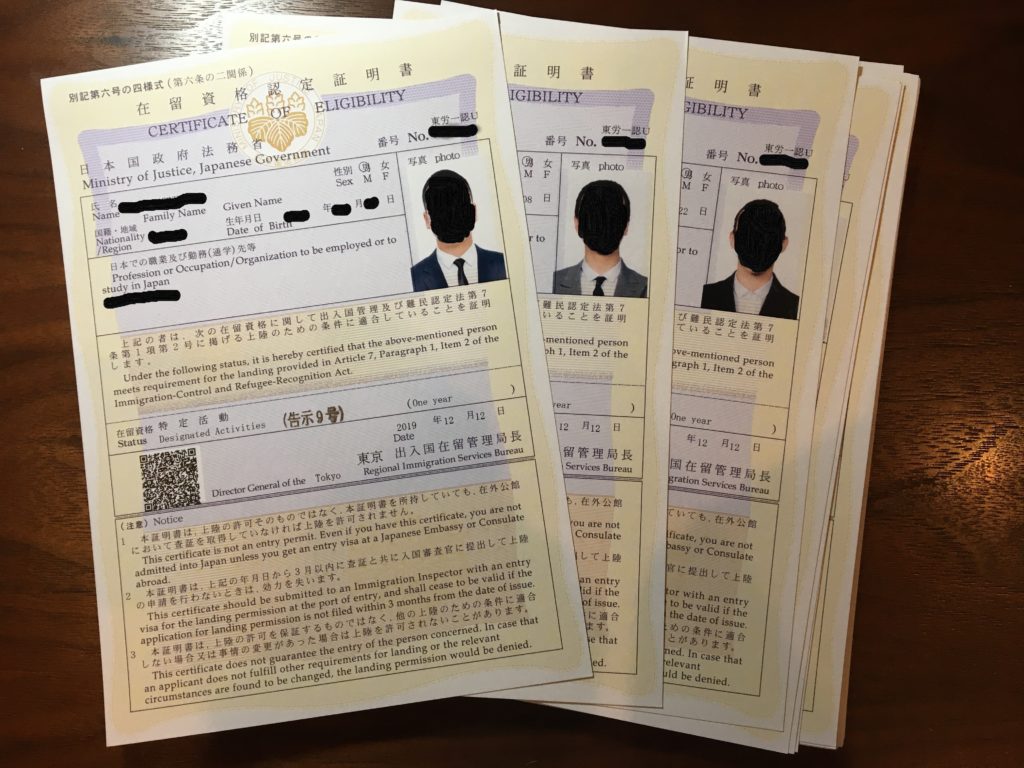3年前に建設業許可を取得した法人様のご依頼により、決算変更の届出を行いました。建設業の許可を取得してから、一度も決算変更届を提出していませんでしたので、3期分まとめての届出となりました。
本来は、建設業法により、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届の提出が義務付けられています。決算変更届を毎年提出していないことのデメリットとして、5年ごとの更新が受けられなくなります。ちなみに、許可更新は、1日でも期限を過ぎると一切受け付けてもらえません。すなわち、せっかく取得した建設業許可が無効となり、再度新規取得することとなります。
決算変更届の提出書類に「工事経歴書」と「財務諸表」があります。どちらもとても重要なものです。記入方法にもルールがあります。特に損益計算書は、税理士が作成する損益計算書とは違い、建設業用に書き換えなけれなりません。税理士でも作成できない方もいます。実務をこなせる行政書士に依頼するのが賢明です。
もうひとつ決算変更届の提出書類に「納税証明書」がありますが、納税証明書は、過去3年分までしか取得できません。そのため、決算変更届を4年間提出していなかった場合、1期分については納税証明書が取得できないため、代わりに「始末書」を提出することになります。決算変更届の提出期限におくれて提出すると、届出書の表紙に「期限内定提出指導済み」という青色のスタンプを押されてしまいます。
何にせよ、提出期限の決められているものは、必ず期限内に提出することです。