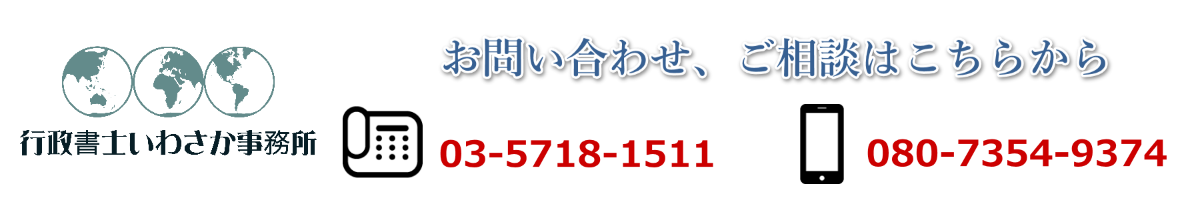⧉ 経営事項審査![]()
経営事項審査とは、日本の建設業において、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査で、公共事業を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。公共事業を発注する行政側が、受注する業者を選択する場合の基準となります。
建設業法第4章の2に定める「建設業者の経営に関する事項の審査等」になります。同法第27条の23では第1項で「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」と規定され、第2項では経営事項審査は、「経営状況」及び「経営規模等」(経営規模、技術的能力、その他の客観的事項)について数値による評価をすることにより行う」と規定しています。また、第3項では「経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。」と規定しており、制度改正には必ず中央建設業審議会が開催されることになります。
⧉ 経営事項審査の流れ![]()
経営事項審査は、建設業の許可業者を対象として行います。申請を希望する業種ごとに許可を持っていなければ申請できません。
1.決算変更届の提出
建設業許可を受けている事業者は決算日から4か月以内に決算変更届を許可をもらっている行政庁に対して提出しなければなりません。
2.経営状況分析機関へ財務諸表を提出
財務諸表を経営状況分析機関提出し、財務状況を点数化してもらいます。この経営状況分析機関というのおは国土交通省に認可された民間の法人が行っています。どこで受けても点数は変わりません。手数料や分析結果が出るまでの時間は、各機関によって違いはあります。
3.経営規模等評価申請書を提出
経営状況分析結果通知書が分析機関から届きます。その通知書を添付したうえで、地方整備局など許可を受けている役所に対して経営規模等評価申請書を提出します。受理されたのち、1か月程度で経営事項審査の結果が届きます。
公共工事を受注したい建設業者はこの経営事項審査を受けることが義務付けられています。有効期間は審査基準日(通常は決算日)から1年7ヶ月間。また、有効期間内に審査事項が変更になった場合、再審査を受けないと不利益をこうむることがあります。
・この経審の総合評定値を客観点とし、これに各官庁・地方自治体等の独自の基準(主観点)を加えた総合点数で、入札ランクを決定する官庁・地方自治体等がほとんどとなります。
・審査行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)が定めた添付書類を基に審査され、ペーパーカンパニーや暴力団関連の建設業者、いわゆる不良不適格業者を排除する仕組みを取り入れている。
・審査は、審査基準日における必要項目を評価します。審査を申請する日に審査事項が改善していても、審査基準日においての状況で判断することになります。
・経審は、建設業許可を取得している企業しか受けることができません。したがって、建設業許可の取得のための審査ではなく、公共工事の受注を希望する建設業許可業者が、各官庁・地方自治体等の入札参加資格審査を受けるためのものになります。
・原則、審査基準日の内容1回だけだか、建設業の業種追加で許可を受けたときなど追加業種について、再度、経営事項審査を受審することが可能です。ただし、審査手数料は、追加分だけでなくすべての業種数で計算されることになります。
審査項目
総合評定値=P点を一定の計算式によって申請業種ごとに出す。計算式と要素は下記のとおり。
P=0.25×X1+0.15×X2+0.2×Y+0.25×Z+0.15×W
● 工事種類別年間平均完成工事高評点 (X1)
申請した工事種類ごとに算出。2年平均(激変緩和措置により3年平均を選択することも可)。
● 自己資本額及び平均利益額 (X2)
自己資本額は、基準決算における純資産合計(激変緩和措置により2期平均を選択することも可)の絶対額で審査される。平均利益額は、利払前税引前償却前利益の2年平均の額で審査される。利払前税引前償却前利益とはEBITDAのことで、経審では営業利益の額に減価償却実施額を加えたものと定義しており、2年平均の額をもって審査される。
● 建設業種類別技術職員数及び工事種類別年間平均元請完成工事高評点 (Z)
技術職員数評点は、申請した建設業の種類ごとに審査基準日現在の人数で算出する。評価対象技術者と点数は、1級技術者(一級建築士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士等)で監理技術者資格者証の交付を受けており、直前5年以内に監理技術者講習会を受講している者(1級監理受講者)が6点、1級技術者であって1級監理受講者以外の者が5点、基幹技能者であって1級技術者以外の者が3点、2級技術者であって1級技術者及び基幹技能者以外の者が2点、その他の技術者が1点である。ただし、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は2つまでである。
工事の種類別年間平均元請完成工事高評点は、申請した工事種類ごとに算出。2年平均(激変緩和措置により3年平均を選択することも可)。激変緩和措置については、X1において選択したものと同じパターンが自動的に適用される。
● 経営状況評点 (Y)
決算書の財務内容を数値化する。
| 項目 | 指標名 | 分子 | 分母 | 上限値 | 下限値 | 意味 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債抵抗力指標 | 純支払利息比率(Y1) | 支払利息−受取利息配当金 | 売上高×100 | -0.3% | 5.1% | 収入に占める実質的な金利負担の割合 |
| 負債抵抗力指標 | 負債回転期間(Y2) | 流動負債+固定負債 | 売上高÷12 | 0.9か月 | 18.0か月 | 期末の負債総額が何か月分の売上高に相当するか |
| 収益性・効率性 | 総資本売上総利益率(Y3) | 売上総利益 | 総資本(2期平均) | 63.6% | 6.5% | 調達した資金によって、主に工事現場でどれくらいの利益を残せたか。ただし、2期平均の額が3000万円未満の場合は3000万円とみなす。 |
| 収益性・効率性 | 売上高経常利益率(Y4) | 経常利益 | 売上高×100) | 5.1% | -8.5% | 売上高から、現場の経費、販管費、財務活動(利息の受け払い)も加味して、どれくらい利益を残せたか |
| 財務健全性 | 自己資本対固定資本比率(Y5) | 自己資本 | 固定資産×100 | 350.0% | -76.5% | 固定資産を自己資本で調達しているか |
| 財務健全性 | 自己資本比率(Y6) | 自己資本 | 総資本×100 | 68.5% | -68.6% | 自己資本の充実具合 |
| 絶対的力量 | 営業キャッシュ・フロー(絶対額)(Y7) | 経常利益+減価償却実施額−法人税、住民税及び事業税±引当金増減額?売掛債権増減額±仕入債務増減額?棚卸資産増減額±受入金増減額 | 1億 | 15.0億円 | -10.0億円 | いくらのキャッシュを1年間で生み出せるのか(1億円単位)。ただし、分子は2年平均。分母は千円単位であれば100000、百万円単位であれば1000。 |
| 絶対的力量 | 利益剰余金(絶対額)(Y8) | 利益剰余金 | 1億 | 100.0億円 | -3.0億円 | 利益の蓄積、すなわち利益の内部留保の絶対規模(1億円単位)。ただし、個人の場合は、利益剰余金を純資産合計と読み替える。分母は千円単位であれば100000、百万円単位であれば1000。 |
以上の8指標を次の算式に当てはめ、経営状況点数(A)を算出
経営状況点数(A)=(-0.4650*Y1)-(0.0508*Y2)+(0.0264*Y3)+(0.0277*Y4)+(0.0011*Y5)+(0.0089*Y6)+(0.0818*Y7)+(0.0172*Y8)+0.1906
このAを他の指標(X1、X2、Z、W)と評点の桁や平均の水準を合わせるために、Yに変換するものが次の式である。
経営状況評点(Y)=167.3*A+583(Yが0点未満の場合は0点とみなす)
この結果、Yの最高点は1595点、最低点は0点となる。
その他の審査項目(社会性等)評点 (W)
・雇用保険加入の有無(減点項目)・健康保険及び厚生年金保険加入の有無(減点項目)・建設業退職金共済制度加入の有無(加点項目)・退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無(加点項目)・法定外労働災害補償制度加入の有無(加点項目)・営業年数・防災協定の締結の有無・営業停止処分の有無・指示処分の有無・監査の受審状況・公認会計士の数・建設業経理士1級の数・建設業経理士2級の数・研究開発費
以上の項目で評価します。
営業年数だけは黙っていても増えますが、逆に言えば長く経営していることだけで評価されることになってしまいます。(ただし、35年で60点が上限)。このほか、平成18年5月改正で防災活動への貢献の状況が追加されました。これは、国・地方公共団体等と災害時における防災活動について定めた防災協定を締結している建設企業に対し15点加算されるものです。通常は、建設業協会等の業界団体が締結していることが多いため、その会員企業であれば加点評価されます。このほか、2008年4月改正で法令順守の状況が追加され、営業停止は30点減点、指示処分は15点減点となっています。